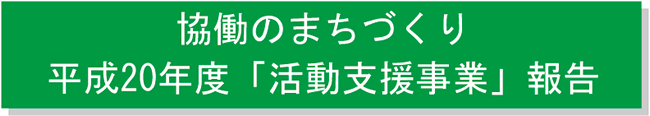
「北中城村村民提案制度 活動支援事業」について、提出された事業実績報告を公表します。
事 業 名:国頭村奥〜屋宜原間タスキリレー
事業の内容:(抜粋)
同事業は、縁があって国頭村奥集落との交流事業として始めたのが始まりで、10年間に1度開催しており、今年で3回目の実施である。初日に屋宜原区民の数名が奥集落に宿泊し、景観美化の講習会や奥集落との交流会をもつ。翌日、奥集落の国道58号の起点から屋宜原自治会事務所までの間を子ども達や青年、老人と各自に合わせた区画を割り振りして、駅伝方式で走り抜き、到着する自治会事務所では、多くの自治会の皆さんの出迎えを受けて、その後、各年齢を超えた交流会を行う。
|
 |
||||||||||||
事 業 名:普天間川河川(石平地区)景観美化・浄化活動
事業の内容:
- 普天間川下流部分(200m程)の桜植樹と花の植え付け
- EMによる河川浄化
- 近い将来、石平地区で桜まつりを開催することを目標に、会員相互の親睦も深めることを目的とした先進地視察研修(沖縄県北部(やんばる))を行う。
|
 |
||||||||||||

「喜舎場の石獅子」
(村指定有形民俗文化財)−喜舎場−
県道81号線を村役場から石平交差点向けにいくと、右側に米軍ゲートがあります。 米軍によって造成される以前、このゲートの手前側(儀間原)には、カニサンと呼ばれる巨岩がありました。カニサンは、喜舎場集落に災いをもたらすフィーザン(火山)であると信じられ、この霊力を封じる返し(ケーシ、フィーゲーシ)として据えられたのがこの石獅子です。
以前は、集落の南西側の俗称ビンダマーチュー(喜舎場23番地付近)に設置されていましたが、現在は喜舎場公園内に移設されています。 獅子を魔除けまたは守護神として用いる習俗は、遠くオリエントに起源があると言われ、沖縄には中国との交流が盛んであった14〜15世紀頃にもたらされたものと考えられています。屋根に獅子像を据えて魔除けとする習慣は、瓦葺き建築が盛んになる明治時代以降に一般に浸透していきました。
喜舎場の石獅子がいつごろ造られたのかはっきり分かっていませんが、山や巨岩に対する除災信仰を知る上で重要な文化財です。
(平成7年6月16日指定)
 細かい表情がわかりますか? |
 喜舎場公園内から、カニサンの方を向いて設置されています。 |