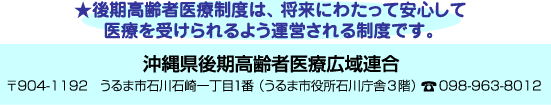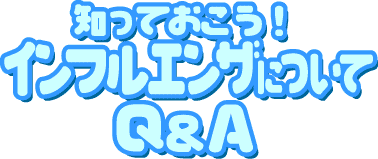


 インフルエンザと普通の風邪はどう違うのですか?
インフルエンザと普通の風邪はどう違うのですか?
A1 インフルエンザは、普通の風邪と同じように、のどの痛み、鼻汁、咳などの症状も見られますが、38℃以上の発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛など全身の症状が突然現れます。熱が出たらできるだけ早く病院に行って治療を受けてください。
 インフルエンザはどのようにうつりますか?
インフルエンザはどのようにうつりますか?
A2 感染した人の咳、くしゃみ、つばなどの飛沫とともに放出されたウイルスを鼻やのどから吸い込むことによって感染します。「咳エチケット」を参考に周りの方へ配慮をしましょう。


●咳やくしゃみなどの呼吸器症状がある方は、必ずマスクを着用しましょう。
●咳やくしゃみをするときは、ハンカチや ティッシュで口や鼻を押さえ、風邪やインフルエンザの原因となるウイルスの飛散を防ぎましょう。
●使用したティッシュなどは、ゴミ箱に捨てましょう。
●咳やくしゃみをした後は、石けんを使用して、よく手を洗いましょう。
 インフルエンザにかかった後、他人にうつらなくなるのは、いつごろからですか?
インフルエンザにかかった後、他人にうつらなくなるのは、いつごろからですか?
A3 症状が現れてから2〜7日間はウイルスを体の外に出すと言われています。外出は控えましょう。
 インフルエンザの予防法(家庭や職場)
インフルエンザの予防法(家庭や職場)
A4 予防接種を受ける、こまめに手洗いやうがいなどを行います。又、空気が乾燥するとインフルエンザにかかりやすくなるので、部屋の中を加湿器などで適度な湿度(50〜60%)に保ちましょう。空気がこもっていると、ウイルスが比較的長い時間空気中を漂っていることがあるので、換気も忘れずに。
予防接種法に基づく対象者
65歳以上の方(60〜64歳の方で心臓・腎臓・呼吸器に重度の障害のある方を含む)は自己負担1,000円でインフルエンザの予防接種ができます(生活保護世帯の場合は自己負担免除)。接種場所は、中部地区医師会加盟の医療機関です。各自お問い合わせください。
 タミフル(インフルエンザ治療薬)の服用について
タミフル(インフルエンザ治療薬)の服用について
A5 10歳以上の未成年者においては、因果関係は不明であるものの、本剤の服用後に異常行動を発現し、転落等の事故に至った例が報告されていることから、合併症、既往歴等からハイリスク患者と判断される場合を除いては、原則として10代の小児・未成年者には本剤の使用を差し控えることとなっています。
【問い合わせ】村役場 健康保険課 健康対策係 TEL935−2233(内線268)


75歳(一定の障害がある方は65歳)以上の人は、国保や、会社の健康保険などの医療保険に加入し、「老人保健」で医療を受けていますが、平成20年4月からは高齢者だけの新しい医療制度「後期高齢者医療」で医療を受けます。
●沖縄県内に住む、75歳(※一定の障害がある人は65歳)以上の人全員が新しい制度の対象です。
※現在、障害認定を受けている人は、引き続き広域連合の認定を受けたものとみなされます。ただし、障害認定を受けている75歳未満の人は、認定を取り下げることもできます。(認定を取り下げる申請は、各市町村窓口へ)
●新しい被保険者証が1人に1枚交付されます。(平成20年3月に対象者へ交付します。)
●お医者さんにかかるときの窓口負担は、これまでの老人保健制度と変わりありません。
●沖縄県内の全ての市町村が加入する、「沖縄県後期高齢者医療広域連合」と「市町村」 が協力して運営します。
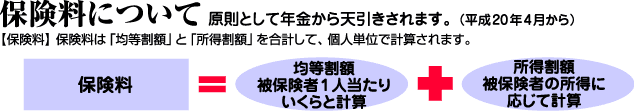
(75歳以上単身世帯の場合)
|
年金収入額
|
均等割額
|
所得割額
|
合計(年額)
|
年金収入額の説明
|
|
4万8,440円
|
8.80%
|
|||
|
62万7,000円※1
|
1万4,532円
(7割軽減) |
0円
|
1万4,532円
|
※1県国民年金平均額 |
|
153万円※2
|
0円
|
1万4,532円
|
※2所得割額のかからない上限 |
|
|
168万円※3
|
1万3,200円
|
2万7,732円
|
※37割軽減の上限 |
|
|
176万3,000円※4
|
3万8,752円
(2割軽減) |
2万504円
|
5万9,256円
|
※4県厚生現金平均額 |
|
203万円※5
|
4万4,000円
|
8万2,752円
|
※52割軽減の上限 |
|
|
220万円
|
4万8,440円
|
5万8,960円
|
10万7,400円
|
※単身世帯の場合は、5割軽減は適用されない。
◆保険料は、世帯構成等によって異なります。
詳細は市町村窓口、または後期高齢者医療広域連合へお問い合わせください。
【所得の低い人の軽減措置】
所得の低い人は、保険料の均等割額が世帯の所得水準にあわせて、7割・5割・2割軽減されます。
【被扶養者の軽減措置】
これまで被用者保険(会社などの医療保険)の被扶養者であった人については、平成20年4月から9月までの半年間保険料が免除され、平成20年10月から平成21年3月までの半年間は9割を軽減します。
また、その後も被保険者となったときから2年間経過するまでは、保険料の均等割額が半額となります。